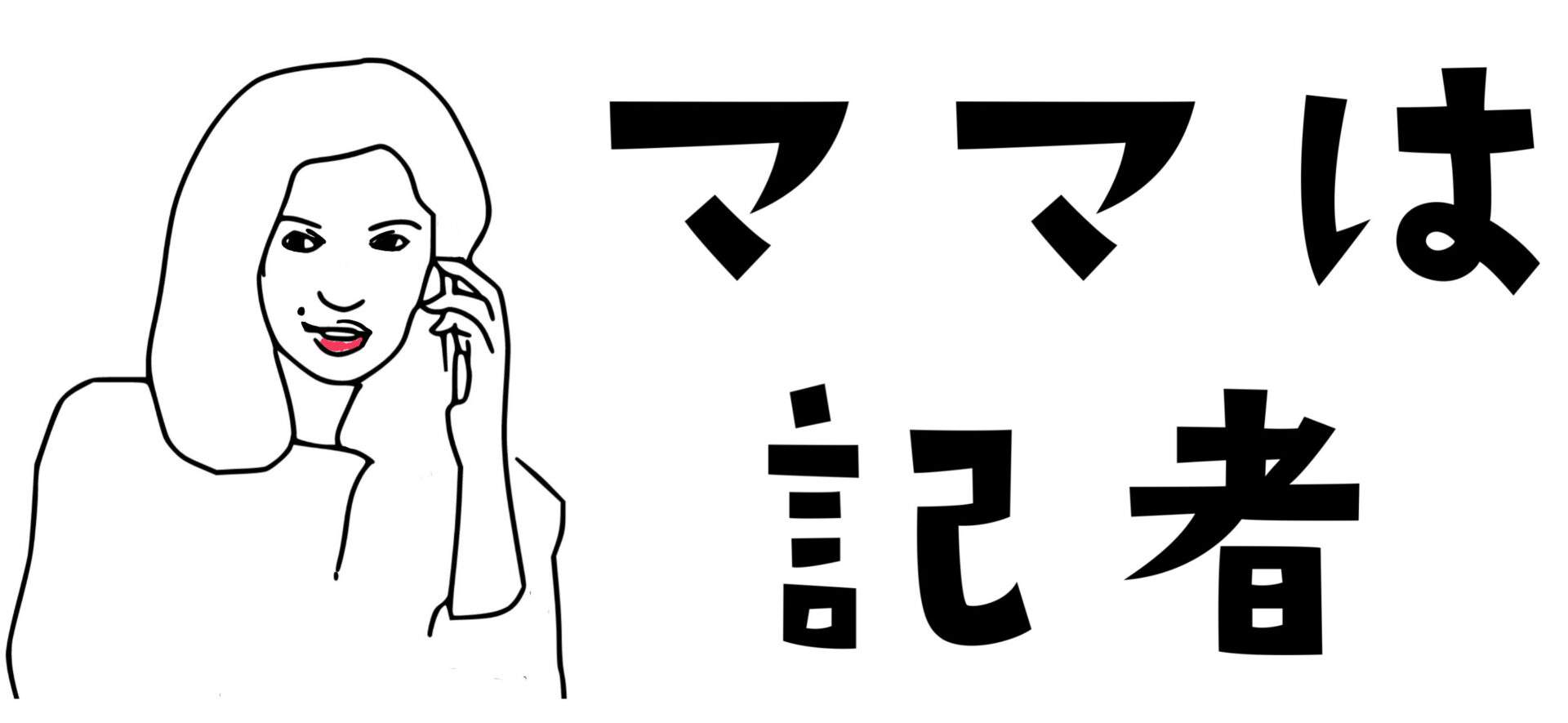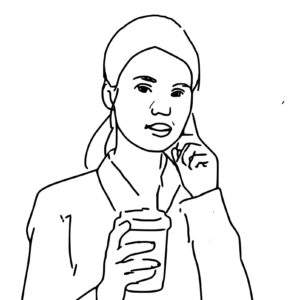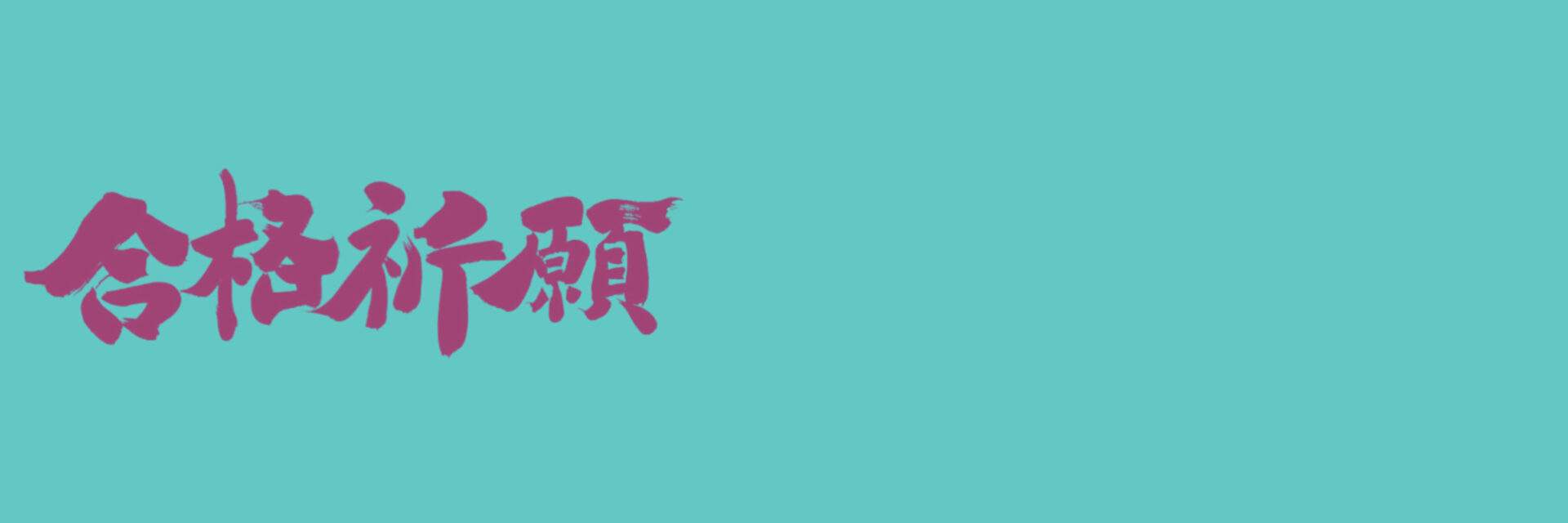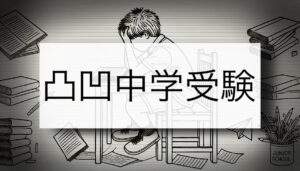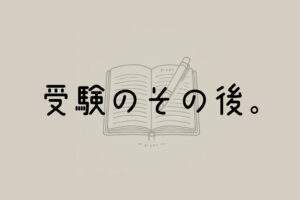凸凹中学受験で起きたこと(続き)
その4 10歳の壁と癇癪と不登校
 太郎
太郎凸凹中受、ついに終わった!
白目太郎の中受のこれまで
小4でS入塾。S偏55からスタート。同年、発達特性と高IQが判明。ADHD薬の服薬で落ち着きのなさはおさまり、クラスはαに上昇。
小5秋に大失速、サピックス退塾。転塾、再度の退塾を経て小6の夏前からサピックスに復帰。復帰時のS偏差値は54。11月にS偏68を突破し、志望校を開成中学に変更、合格した。
正直、凸凹育児なんて壁だらけなのだが、この10歳の壁は我が家にとっては一際高かった。
9歳から10歳というのは、子どもにとって大きな転換期らしい。それまでの具体的な世界から、少しずつ抽象的な思考が求められるようになり、物事を客観的に捉える力が育つ時期であり、 同時に「今までのやり方では通用しない」という壁にぶつかる時期でもある。分解すると、四つの壁があったと思う。
一つ目は、学習の壁。例えば、算数。長男はもともと計算は得意だったが、分数や割合といった抽象度の高い概念が増えるにつれ、これまでの直感的な理解だけでは乗り切れなくなった。新しい概念を取り込むのが苦手で、親に教えられるという状況にも拒否感を示した。習うより慣れろ、とにかくやればできると言われることに強い苛立ちを感じた。
二つ目が、自己評価の壁。自己評価が厳しくなり、周囲との比較を意識するようになったことで、劣等感を抱きやすくなった。鉛筆をバキバキに折ったり、解いている問題集をビリビリに引き裂くなどの癇癪は日常茶飯事。親への反発から大変な口論に発展することも多かった。
三つ目が、周囲とのギャップの壁。知的好奇心が強く、理解が早いがゆえに、学校の授業が耐え難いほど退屈になる。単に「つまらない」ではなく、「なぜこんな無駄なことをやらなければならないのか」という疑問が膨らみ、学校というシステムそのものへの不満が募る。不登校傾向が強まったのもこの頃からだ。
長男の場合、ASD傾向や正義感の強さも相まって、周囲とのズレがより一層ストレスになった。一部の同級生の行動が「幼すぎる」と感じ、「なぜあんなことをしても許されるのか」という苛立ちを抱えるようになった。トラブルを避けるため、「周りのことは気にせず、スルーするように」と親から助言しても、本人には受け入れ難かった。周囲が気になって仕方がないのに、どうすることもできない。そのジレンマが、さらに学校を遠ざける要因になった。
四つ目が、非同期発達の壁。知的な発達と身体の発達とのギャップがあり、頭の中ではスムーズに解けているのに、いざ手を動かすとうまくいかない。筆算を書こうとすると手が止まる。文章題の答えはすぐ出るのに、途中の式を書こうとするとわからなくなる。本人曰く、「僕は分かっているのに、手が勝手に間違える」「手がめんどうくさがる」という感覚。
自分が「できない」ことに対する怒りは、単に勉強が難しくなったからではなく、「できるはずなのに、できない」というギャップへの苛立ちだった。そして、「こんなはずじゃないのに」と自分に苛立ち、最後は大癇癪。この繰り返しに、子供も親も激しく疲弊した。
以下は今後書きたいことのリスト。
今日も授業に行けない!10歳の壁と癇癪と不登校ケアレスミスとの戦い「眠い・疲れている」が分からない授業点が取れない教材以外で学ぶあと伸びを信じる成績の停滞は「慣れ待ち」投薬の効果- 5年秋で凸を見極め
- 記述対策で伸びる
- プロのアドバイスに従え