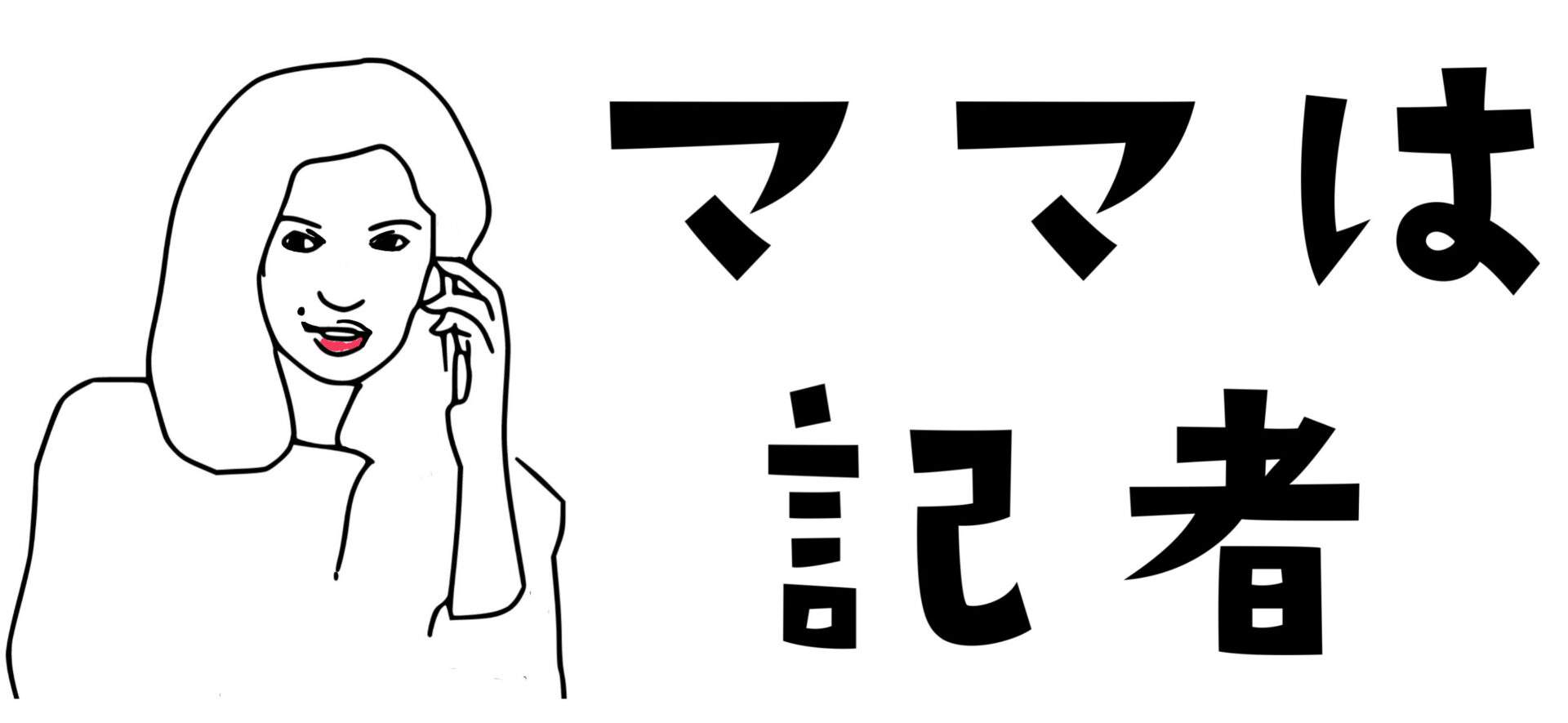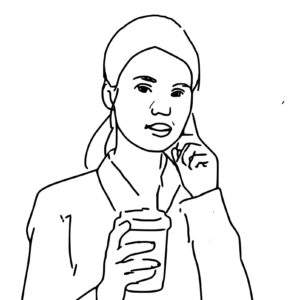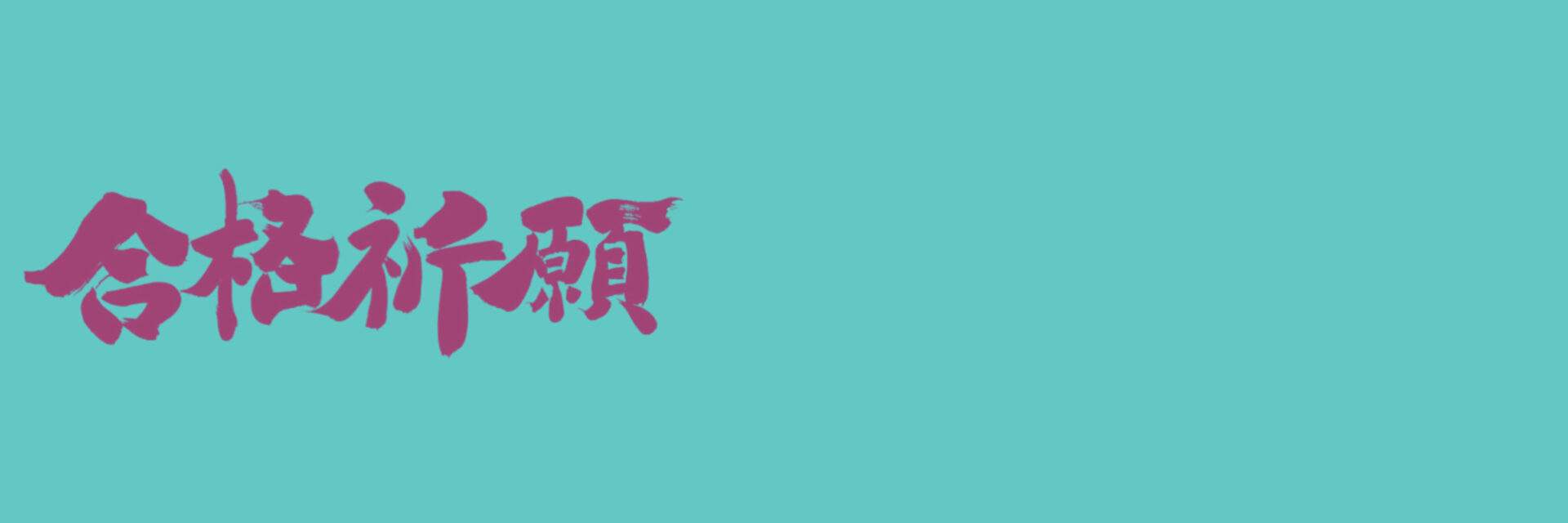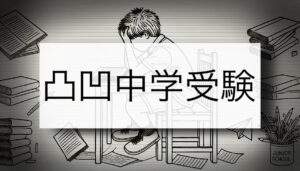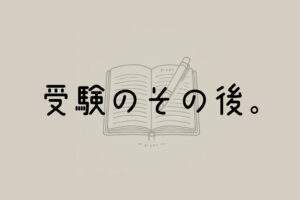凸凹中学受験で起きたこと(続き)
その6 「眠い・疲れている」が分からない
定型の子どもなら、「眠い」「疲れている」と言えばそのままの意味で受け取れる。夜更かししたから眠い、運動したから疲れている。当たり前のことだ。しかし、長男にはこれが通じなかった。「疲れているから休む」という発想がないだけでなく、もっと言えば、「自分が今、疲れている」という状態を認識すること自体が難しいらしい。
さらに厄介だったのは、「眠い」や「疲れた」という身体的な不調が、そのまま「嫌だ」という漠然とした感情に置き換わり、塾に対するネガティブな記憶として積み重なってしまうことだった。
たとえば、塾の授業中に眠くてぼんやりしていたり、疲れて集中できなかったりすると、本来なら「今日は眠かったからうまくいかなかったな」と振り返るところを、「塾、嫌だった」「塾に行くとしんどい」と感じてしまう。
つまり、「眠い」「疲れた」という感覚が、自分の中で正しく言語化されていない。しかし、その不快感を言語化しようとはする。その結果、目の前に見える先生や授業の内容が原因であると「解釈」して、理由をこじつけてしまう。本来は身体的な不快感が原因であったはずなのに、「塾が」「授業が」だめだったと決めつけてしまい、拒否反応につながっていく。長男が何かを拒否しはじめる時、その背景にはこういうサイクルがあったように思う。
ここでは仮に「眠い」「疲れている」としたが、ここにはさまざまな感情や感覚が入る。「鼻水が出て集中できない」もそうだし、「光が眩しくて目がチカチカする」そうだ。お腹が空いている、喉が渇いている、ありとあらゆる「不快感」が「不機嫌」「拒否」の原因になる。
この感覚の鈍さや内省能力の低さは、親からの支援をかなり困難にした。こちらからすると、「何が原因でそんなに機嫌が悪くなっているのか分からない」のに、対応しようとする親に悪態をつきながら、あっという間に猛獣と化すのだ。五感の情報は混乱してるのに、言語化能力だけが不釣り合いに高いと、こうなりがちなんじゃないか。多分だけど。
ちなみに、この感覚への鈍さに気がついたのは、テキストをたくさん詰め込んだリュックを背負って、ショッピングモールに行った時の大癇癪がきっかけだった。手に負えないほどの不機嫌を撒き散らしていたのに、荷物をロッカーに入れてクレープか何かを食べさせたら、あっという間に機嫌が回復した。「もしかして、お腹が空いていて荷物が重かっただけ?」と気がつき、目が点。そして、遅ればせながら、これまでの数多くの癇癪も、「単に何かが不快」というレベルで起きていたこともあったのでは、と気付かされたのだ。
遅いよ…と思われる方もいるかもしれないが、長男の場合は「ポジティブな感情も強い」という点が発見を困難にした。多少の不快感があっても、楽しみなことがあると、相殺できてしまう。塾の授業に耐えられる理由はまさしくこれ。知的好奇心が強い彼には、授業自体は基本的に楽しいもの。身体が送るシグナルを無視するほど没頭できてしまう。
これは一見、問題の解決につながったように見えるため、これまでは、どちらかというと、「不機嫌な長男を楽しい場に連れ出す」「楽しい気持ちになれるものを探す」という発想からの対応が主で、「不快を取り除く」という視点を持っていなかった。
それにしても、普通の人が適度にガス抜きしながら機嫌よく過ごせるのは、刺激の処理がスムーズに行われ、見えないところで細かい調整が行われているからだ。普通の子が何気なくできることも、長男にとっては意識しないと難しい。この感覚の混乱に気づき、少しずつ調整できるようになったのは、小6になってからだった。
以下は今後書きたいことのリスト。
今日も授業に行けない!10歳の壁と癇癪と不登校ケアレスミスとの戦い「眠い・疲れている」が分からない授業点が取れない教材以外で学ぶあと伸びを信じる成績の停滞は「慣れ待ち」投薬の効果- 5年秋で凸を見極め
- 記述対策で伸びる
- プロのアドバイスに従え