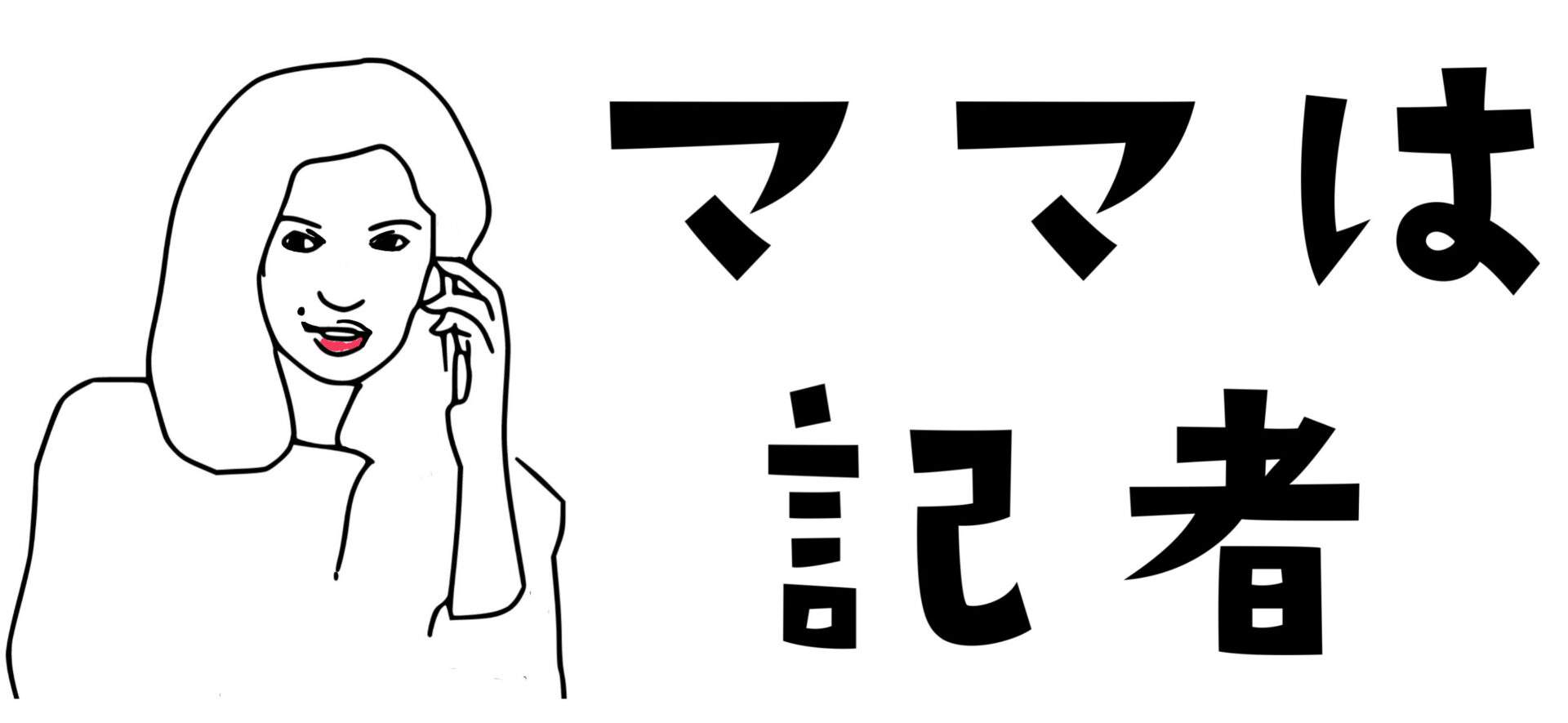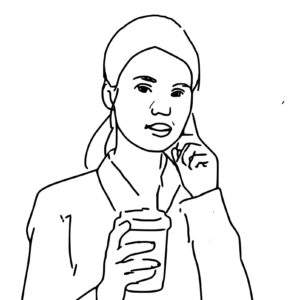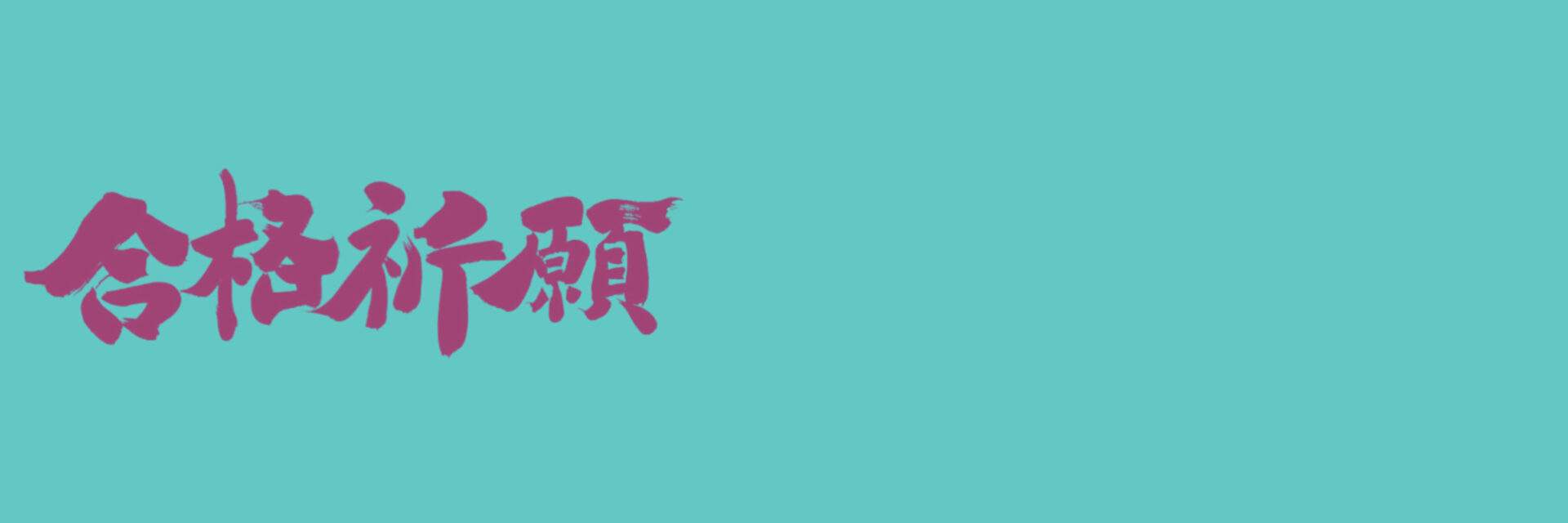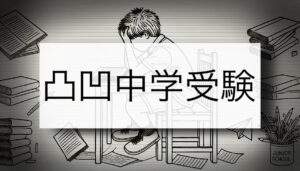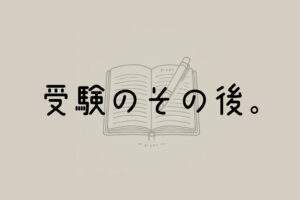凸凹中学受験で起きたこと(続き)
その9 4年時点の成績では、子どもの到達点はわからない
今回は社会以外の科目での凸の見極め方について書くつもりだったが、ちょっと思うことがあったので追加する。
「あと伸びを信じる」ということについて。
きょう、Xで以下の投稿が話題になっていた。みなさんご存知、戦記さんの発信である。
引用を引用してさらに引用しているので、ややこしいが、要は「小学4年生時点の成績がそのまま6年生の成績になる」か否かが論点だ。
すべてのことに例外はあるので、例外の存在をもって、戦記さんの発信を否定したいわけではない。戦記さんも、引用元も、「多くの場合」「ほとんど」という言い方をしていて、例外の存在する余地は残しているので、我が家の経験とは矛盾しない。
長男のケースは少数派に属するということだが、数%の狭い道を足掻いてきた身としては、「珍しいケース」で片付けてしまうのは、あまりにももったいない。少数派とはいえ、10%もいればそれなりに存在するし、だからこそ、同じ道を歩む誰かの道標になればと思い、私はこの記録を残している。
特性のある子どもは、一般的な「この時期にこう伸びる」という成長曲線には当てはまらないことが多い。長男もそうだった。S偏差値55あたりをウロウロし、そこから伸びる兆しはなかった。
これがとても難しいところで、親からするとその時の長男は、その時の偏差値なりの地頭に見えた。思考力が必要な問題には拒否感を示し、解説を聞いても「へえ、そうなんだ」と流して終わり。新たな技術が必要な問題でも、習った解き方を試そうとすらせず、それまでのやり方に固執しては、何度も間違えた。あと伸びするような兆候は全くなかった。
でも、その後、伸びた。
長男が6年後半に入ってから伸びた理由はいくつかあるが、一つにはADHD薬が合い、彼が能力を発揮しやすくなったというのは大きい。ただ、それだけではなかった。成長により、認知力と出力の精度が上がり、記述方式の問題でも整理して書けるようになったというのもあった。
今振り返ると、4年時点での失点は、脳内の処理を適切に出力できないことによるものだったのだと思う。知識を中心の理社では起こりにくいが、問題を見た瞬間に頭を働かせ始める算数で、失点が顕著だった。分かるはずなのに焦って間違える、設問を読み違える、答えを書き損ねる。「分かるのにできない」状態。こうした「アウトプットの精度」の問題が、6年後半になってようやく改善されていった。
だからこそ、「4年時点の成績では、子どもの到達点を決められない」と私は思う。4年時点では「できなかった」ことが、6年になって「できるようになる」ことは、特性のある子にとっては珍しくない。長男のように、6年の秋以降に一気に成績が変わることもある。もちろん、全員がそうなるわけではないが、「あと伸び」は特定の子どもにとっては、確かに存在する。
以下は今後書きたいことのリスト。
今日も授業に行けない!10歳の壁と癇癪と不登校ケアレスミスとの戦い「眠い・疲れている」が分からない授業点が取れない教材以外で学ぶあと伸びを信じる成績の停滞は「慣れ待ち」投薬の効果- 5年秋で凸を見極め
- 記述対策で伸びる
- プロのアドバイスに従え